糖尿病の差別をなくす取り組み~スティグマとアドボカシーの観点から~
第1回 スティグマとは
関西電力病院 糖尿病・内分泌代謝センター 部長
公益社団法人日本糖尿病協会 企画・啓発委員
田中 永昭 先生
スティグマの構造:糖尿病のない人からの分断
スティグマとは「恥・不信用の烙印」という意味で、否定的な価値を付与するというニュアンスを含みます。糖尿病の診療をめぐる課題として、糖尿病の診断がついた瞬間からその人はしばしばスティグマを受けることになり、糖尿病ではない人との分断にさらされがちであることが問題視されています。分断の原因は、家族・同僚・社会・医療者の不十分な知識・理解であり、家族や同僚からは「自己管理ができていないせいだ」といった非難、社会からは住宅ローンを組めないなどの差別、医療者からは不適切で厳格な食事管理といった制限などを受けることがあります。その結果、糖尿病のある人は社会からの疎外を感じたり経済的な不利益を被ったりし、そのような環境下では治療に向き合えず、自尊感情までもが低下することになりかねません。
スティグマの歴史
「スティグマ」はギリシャ時代にできた言葉です。当時は奴隷や罪人に押された焼き印のことを指しており、社会的に忌避すべきものを知らしめる目印でした。現代では1963年にアメリカの社会学者のGoffmanが「恥や不信用の烙印」と表現しており1)、社会規範から逸脱したアイデンティティーを蔑むニュアンスが込められています。また、Goffmanは、糖尿病はスティグマを生みうる病気であるということも指摘しています1)。
日本では、2019年にアメリカ糖尿病協会からスティグマの認知とアドボカシー*活動の取り組みが不十分であるという指摘を受けたことを契機として、同年、日本糖尿病協会(以下、日糖協)の清野理事長と日本糖尿病学会の門脇理事長(当時)が、スティグマをめぐる問題解決を目的として、アドボカシー委員会を発足させました。その後、2020年に刊行された『糖尿病治療ガイド2020-2021』には、初めて「スティグマ」「アドボカシー」という言葉が目標に登場し2)、解決すべき課題であるという認識が急速に広まったと実感しています。
*アドボカシー:弱い立場に置かれる人の権利を守るため、組織・行政・立法に対し、主張・代弁・提言を行うこと
スティグマが発生する原因
糖尿病をめぐるスティグマが発生する原因には、社会的側面と医療者的側面があります。
社会的側面について、日糖協では「糖尿病という疾患に対する誤った認識」と「糖尿病の治療の困難さに関する誤った認識」の2つがあると考えています。
前者の認識は、「糖尿病」という名称や、自己責任の病気であるといった誤解から生まれます。「糖」・「尿」・「病」の3字はいずれも否定的なイメージを持つ字ですし、糖尿病は「食事」や「甘いものを食べたい」という人間の欲求と強く結びつけられやすく、「不摂生な人がなる病気」・「欲求をコントロールできない恥ずかしい病気」という誤解が他の疾患よりも生まれやすいと言えます。



後者の認識は、「悲惨な病気」・「長生きできない」というイメージや、糖尿病の治療目標を容易に達成できる方法が乏しい現状に対する理解が不十分であることから生まれます。現在でこそさまざまな治療薬がありますが、100年ほど前はインスリンもまだなかったため、極端な糖質制限が必要だったり、失明や腎不全といった合併症が起こりやすかったりしました。今や治療方法は大きく進歩しているわけですが、一般社会には当時の悲惨というイメージが根深く残ってしまっています。「原因は過食」という印象もありますが、エネルギー摂取量を糖尿病ではない人と2型糖尿病のある人で比較した研究では、両群間で明らかな差がないと報告されています(図1左)3)。また、「寿命が短い」という印象もありますが、男性と女性の40歳時点での平均余命は、日本人全体についての2000年の調査で39.0歳と45.5歳4)、糖尿病のある人についての1995~2001年の調査で39.2歳と43.6歳5)とそれぞれ報告されています(図1 右)。にもかかわらず、このような間違った印象がもたれているのです。一方で、例えば合併症予防のための血糖管理目標はHbA1c 7%未満などと明確な基準が設けられていますが、達成している人の割合は3~4割程度とされています。このように現代の医療をもってしても達成は難しいのに、その現実についての理解が進んでいないことも原因です。
スティグマ発生原因の医療者的側面については、教育機関でスティグマについて学習する機会が乏しいことや、個別性の配慮が難しいことなどが挙げられます。
医療者は、学生時代を含めスティグマの学習をする機会が乏しいように感じます。教科書に掲載されることも、臨床で話題に上る機会も極めて少ないと思います。
また、生活習慣は血糖値に影響する要素の1つですが、人によるバリエーションが多いため、変容が必要になっても何をどう変えたらどの程度効果があるのかといったことを、根拠をもって説明することは難しいのが実情です。結果的に、教科書的な教育をせざるを得ませんが、人によってはその内容が非現実的なものとなります。しかし、医療者は“教科書通りの教育をしているのだから正しい”と考えてしまい、教育内容を遵守できなかった場合は糖尿病のある人にその責任を押し付けてしまう結果になりがちです。


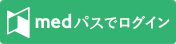
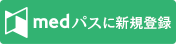


 Diabetes Informationトップ
Diabetes Informationトップ