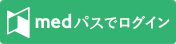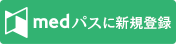今回のテーマは,「ポリファーマシー」です。
ポリファーマシー
 ポリファーマシーに関連する次の記述について,正しいものに〇,誤ったものに×を付けてください
ポリファーマシーに関連する次の記述について,正しいものに〇,誤ったものに×を付けてください
- 何剤以上をポリファーマシーとするか,厳密に定義されている
- ポリファーマシーが起こりやすい典型例として「処方カスケード」がある
- 糖尿病治療薬は「特に慎重な投与を要する薬物のリスト」に含まれている
- ポリファーマシーに対する明確な介入策が確立されている
 答え:1)×,2)〇,3)〇,4)×
答え:1)×,2)〇,3)〇,4)×
解説
ポリファーマシーの定義
何剤以上をポリファーマシーとするか,厳密には定義されていません。厚生労働省は,2017年に高齢者医薬品適正使用検討会を立ち上げ,「高齢者の医薬品適正使用の指針」を公表しました。このなかで,ポリファーマシーを「単に服用する薬剤数が多いことではなく,それに関連して薬物有害事象のリスク増加,服薬過誤,服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」と定義し,薬剤数よりも本質的には中身が重要であるとしています。
厚生労働省.高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編).2018年5月
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/kourei-tekisei_web.pdf
処方カスケード
ポリファーマシーが形成される要因にはさまざまありますが,典型例として,多病による複数医療機関・診療科の受診と,処方カスケードの2つがあります。処方カスケードとは,薬剤の有害事象に気付かず,さらに薬剤で対処し続けていく悪循環の状態をさします。
石田岳史, ほか. 日内会誌 2020; 109: 1002-1008.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/109/5/109_1002/_pdf
糖尿病とポリファーマシー
糖尿病におけるポリファーマシーとしては,加齢に伴い複数の疾患が併存し,互いに影響し合って複雑さを増すマルチモビディティの病態との関連が注目されています。また,「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015」(日本老年医学会編集)には「特に慎重な投与を要する薬物のリスト」が記載されています。これらの薬物は系統的レビューの結果に基づいて選定されたもので,糖尿病治療薬はこのリストに含まれています。
高齢者では低血糖が起こりやすく,また近年はさまざまな作用機序の糖尿病治療薬が登場し,それらの併用療法も行われることから,重症低血糖の発現に注意が必要です。患者さんの病態や併存疾患などに応じて中止・変更できる薬剤はないかを検討し,配合剤や週1回投与製剤,注射剤などを活用することはポリファーマシーの是正につながります。
日本糖尿病学会,日本老年医学会 編.高齢者糖尿病治療ガイド2021.
日本老年医学会.高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015.
https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/topics/pdf/20170808_01.pdf
小田知靖,ほか.内科 2022; 130: 519-522.
ポリファーマシーへの介入策
ポリファーマシーへの介入として,一般的には前述の特に慎重な投与を要する薬物等の薬剤評価や処方見直しが行われますが,それだけでは不十分なこともわかってきました。患者さんの状態を含めた総合的な介入や,薬剤評価に加えて患者さんへの動機付けや地域医療連携等を行う多角的介入も検討されていますが,現在のところ介入策に関する十分なエビデンスはありません。
患者さんの状態を把握するためには,医師,薬剤師をはじめとする多職種間で情報を共有し,患者さん自身にも積極的に医療に参加してもらうことが重要です。患者さんの行動変容を促す方法として,「ナッジ(nudge)」(人々が自発的に最適な選択を行えるよう支援する仕組み)を利用した行動経済学的アプローチ等も検討されています。
厚生労働省では,ポリファーマシー対策の取組みを進めるツールとして,ポリファーマシー対策導入のための業務手順書や導入事例集を作成し,モデル医療機関で実際に運用してもらうことによってその実用性を検証しています。この取組みの結果は2022年4月に報告され,これらツールの有用性や課題,今後整備すべき内容などが確認されました。
石田岳史, ほか. 日内会誌 2020; 109: 1002-1008.
溝神文博.Geriatr Med 2021; 59: 895-900.
厚生労働省.第15回 高齢者医薬品適正使用検討会 資料(2022年4月13日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25107.html