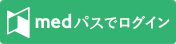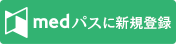今回のテーマは,「生活環境病」です。
生活環境病
 世界保健機関(WHO)の「住まいと健康に関するガイドライン(2018年)」では, 冬季を安全で健康に過ごすための室内温度として何度以上を推奨しているでしょうか。
世界保健機関(WHO)の「住まいと健康に関するガイドライン(2018年)」では, 冬季を安全で健康に過ごすための室内温度として何度以上を推奨しているでしょうか。
- 16℃
- 18℃
- 20℃
- 22℃
 解答:正解は2)
解答:正解は2)
解説
日本の家は寒い
WHOは2018年に「住まいと健康に関するガイドライン(Housing and Health Guidelines)」を発表し,冬季を安全で健康に過ごすための室内温度として「18℃以上」を強く推奨しています1)。この推奨は,日本を含む複数の国の疫学研究を対象とした系統的レビューで,室温18℃未満では18℃以上に比べ呼吸器疾患や心血管疾患のリスクが上昇することが示されたことに基づいています。
日本では,住環境と健康アウトカムの関係に関するエビデンスが少なかったことから2),国土交通省が厚生労働省と連携し,住環境と健康の関係を調査する「スマートウェルネス住宅等推進調査事業(SWH全国調査)」を2014年に開始しました3)。亜熱帯の沖縄県を除く全国2,190世帯を対象に冬季の室温を分析した結果,WHO勧告の18℃以上を満たしていない割合が,居間の室温で6割,就寝中の寝室や脱衣所の室温で9割にものぼっていました4)。また,都道府県別で在宅中の居間の平均室温が最も高いのは北海道(19.8℃),最も低いのが香川県(13.1℃)で,寒冷地よりも温暖地で室温が低いことも明らかになりました。
家が寒いと何が起こる?
室温との関係がよく知られているのは血圧ですが,SWH全国調査では,そのほかにもさまざまな健康アウトカムとの関連が調査されています。就寝前の居間の室温が低いと過活動膀胱の症状がある人が多いこと,居間の室温が低い家では高い家に比べLDL-コレステロール値が基準値を超える人や心電図異常所見がみられる人の割合が高いことなどが示されました2)。また,居間の室温が18℃未満だと関節症・高血圧・糖尿病・脂質異常症などの割合が高いこと,上下温度差(床上1mと床近傍の室温の差)が大きいと糖尿病や高血圧のリスクが上昇することなども明らかとなりました5)。座位行動(座りすぎ)は身体活動とは独立した総死亡,心血管疾患,2型糖尿病などのリスク要因ですが,寒い家では暖かい家よりも座位行動時間が長いことも示されています4)。
この調査では断熱改修前後での比較も行われており,断熱改修によって室温が上昇すると,起床時の収縮期血圧が低下し,過活動膀胱の症状がある人が減少し,住宅内での身体活動時間が増加することなどが明らかとなっています2)。
「生活習慣病」は「生活環境病」でもある
高血圧,糖尿病,脂質異常症や肥満などは個人の生活習慣に関連することから「生活習慣病」と呼ばれていますが,それらの発症には,生活習慣に加え,遺伝的要因や地球温暖化に伴う気候変動,生活空間や環境の変化などさまざまな生活環境因子が関わっています6)。
このような観点から,最近では「生活習慣病」を「生活環境病」と捉える考え方が生まれています3,6)。個人の生活習慣を整えることはもちろん重要ですが,住居や街全体を含めた健康増進のための環境作りも重要であることがわかってきました。たとえば,WHOは2016年に,都市の緑化空間がメンタルヘルスの改善,循環器疾患の有病率や死亡率,肥満・2型糖尿病リスクの低減などに有益であると報告しています7)。
日本でもさまざまな取り組みが始まっており,国土交通省では「健康・医療・福祉のまちづくり」の一環として,「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり(ウォーカブルなまちなかの形成)を推進しています8)。同省のホームページには,「健康まちづくりの事例集」も公開されています9)。
- WHO Housing and health guidelines. 2018.
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/276001/9789241550376-eng.pdf?sequence=1(2023年11月閲覧) - 健康長寿ネット.住宅と健康長寿.
https://www.tyojyu.or.jp/net/topics/tokushu/kenkochoju-ikigai/jutaku-kenkochoju.html(2023年11月閲覧) - 伊香賀俊治(監).“生活環境病”による不本意な老後を回避する―幸齢住宅読本-. 社会保険出版社; 2023.
- 伊香賀俊治.日本不動産学会誌 2021; 35(1): 62-6.
- 厚生労働科学研究費補助金.循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業.健康増進に向けた住宅環境整備のための研究.令和3年度総括・分担研究報告書.
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/download_pdf/2021/202109017A.pdf(2023年11月閲覧) - 伊藤裕.日内会誌 2020; 109: 1837-43.
- World Health Organization. Urban Green Space and Health. 2016. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/345751/WHO-EURO-2016-3352-43111-60341-eng.pdf?sequence=3(2023年11月閲覧)
- 国土交通省.「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり~ウォーカブルなまちなかの形成~.https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000072.html(2023年11月閲覧)
- 国土交通省.健康まちづくりの事例集.
https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001616190.pdf(2023年11月閲覧)