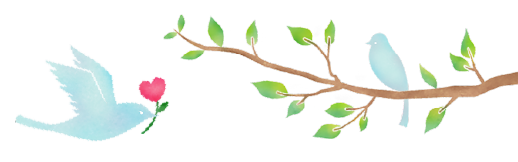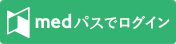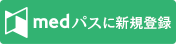今回のテーマは,「睡眠と糖尿病」です。
睡眠と糖尿病
 直近の厚生労働省の実態調査において,20歳以上の日本人の1日の平均睡眠時間として最も割合が多かったのは,次のうちどれでしょうか。
直近の厚生労働省の実態調査において,20歳以上の日本人の1日の平均睡眠時間として最も割合が多かったのは,次のうちどれでしょうか。
- 7時間以上8時間未満
- 6時間以上7時間未満
- 8時間以上9時間未満
 正解は2)
正解は2)
解説
まだまだ少ない! 日本人の睡眠時間
令和元年の「国民栄養・健康調査」1)によると,20歳以上の日本人の1日の平均睡眠時間は「6時間以上7時間未満」の割合が最も高く,男性32.7%,女性36.2%でした。ただし,5時間未満,5時間以上6時間未満を合わせると,その割合は男性37.5%,女性40.6%で,これを性・年齢階級別にみると男性の30~50歳代,女性の40~50歳代で4割を超えていました。また,睡眠の質についての回答では「日中の眠気」「中途覚醒」などが多く,日本人の睡眠は量・質とも十分とはいえません。
世界的にみても,日本人の睡眠時間は短いことがわかります。2021年に経済協力開発機構(OECD)が行った調査では,日本人の1日の平均睡眠時間は7時間22分で,対象となった33カ国の平均の8時間28分を大きく下回り,最下位でした2)。
睡眠不足や不眠症など睡眠障害が疾患リスクを高め生命予後を悪化させるというエビデンスが積み重ねられ,世界的にも睡眠は重要課題に位置付けられるようになった3)ことから,「健康日本21」4)での睡眠の項目・目標値の設定,「健康づくりための睡眠指針2014(睡眠12箇条)5)」の策定など,日本人の睡眠時間減少に歯止めをかけるべく啓発が行われてきました。2024年度からの第3次「健康日本21」始動に向け、睡眠指針の改訂作業「健康づくりのための睡眠指針2023(案)」も進行中です6)。
短時間睡眠と生活習慣病リスク
睡眠は,食事や運動と並ぶ基本的生活習慣の1つであり,体の恒常性維持に重要な役割を担っています。慢性的な睡眠不足は恒常性維持機能の低下を引き起こし,概日リズムの乱れから糖尿病や肥満,心疾患といった心血管代謝系の疾患(cardiometabolic diseases)の発症リスクを高める可能性がある7),と指摘されています。
睡眠不足というストレスが加わると,体は視床下部‐下垂体‐副腎皮質系と交感神経‐副腎髄質系(自律神経系)の2つの反応により恒常性を維持しようとします8)。前者ではコルチゾール,後者ではカテコラミンが血糖値を上昇させ,このことが糖尿病の発症リスクを高める一因になるといわれています。
ほかにも睡眠不足は,免疫システムの攪乱(心血管疾患リスクの一因とされる慢性炎症を惹起)やホルモン分泌異常(食欲抑制作用をもつレプチンの低下/食欲促進作用をもつグレリンの増加),インスリン感受性の低下9)など,さまざまな要因が複雑に絡み合い,生活習慣病リスクの増加をもたらすのです。
睡眠障害と2型糖尿病
短時間睡眠(睡眠不足)や不眠といった睡眠障害による糖代謝への影響は以前から指摘されています3)。健康影響に関するコホート研究の文献レビューによると,2型糖尿病罹患に対する相対リスクは入眠困難で1.6~3.0,中途覚醒で2.2と有意に高いことが報告されています3)。
一方で, 2型糖尿病患者では睡眠障害が高い頻度でみられることから,糖尿病であること自体が睡眠障害の原因となっている可能性も示唆されています10)。糖尿病の罹患により頻度が高くなる睡眠障害には,不眠症,閉塞性睡眠時無呼吸,レストレスレッグス症候群などが挙げられています9)。また,2型糖尿病では血糖コントロールの悪化が睡眠の質低下と相関するという研究結果も報告されています11)。
- 厚生労働省.令和元年「国民栄養・健康調査」結果の概要. https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000687163.pdf(2023年10月閲覧)
- 厚生労働省.「良い目覚めは良い眠りから 知っているようで知らない睡眠のこと」解説書.
http://e-kennet.mhlw.go.jp/wp/wp-content/themes/targis_mhlw/pdf/guide-sleep.pdf?1680307200063(2023年10月閲覧) - 土井由利子.保健医療科 2012;61:3-10.
- 厚生労働省.健康日本21 (休養・こころの健康). https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kenko21_11/b3f.html(2023年10月閲覧)
- 厚生労働省.健康づくりための睡眠指針2014(睡眠12箇条).平成26年3月. https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000047221.pdf(2023年10月閲覧)
- 厚生労働省.第2回健康づくりのための睡眠指針の改訂に関する検討会. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35535.html(2023年10月閲覧)
- Rangaraj VR, et al. Sleep Med 2016 February;18:19-35.
- 豊浦麻記子 ほか.脳と発達 2022;54:311-16.
- 刑部彰一 ほか.日内会誌 2021;110:753-60.
- 田尻祐司 ほか.糖尿病 2022;65:497-504.
- Yoda K, et al. PLoS One 2015;10:e0122521.