- お役立ち情報
- キッセイ診療サポート
![]()
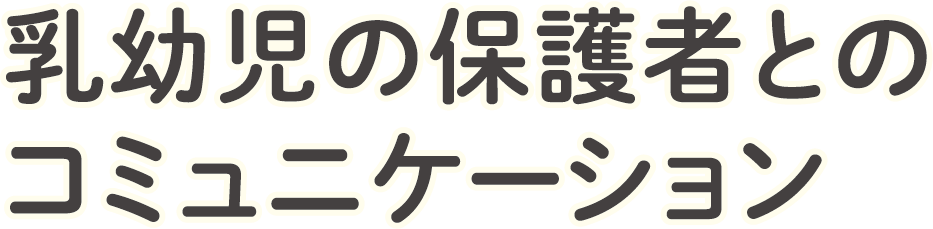
子どもへの服薬に苦労する保護者にできる支援とは?
乳幼児の保護者とのコミュニケーションについて考えます。

監 修坂口 眞弓 先生 みどり薬局[東京都台東区蔵前]
子どもが薬を飲むのを嫌がり困っている保護者は少なくありません。また、子どもに服薬させた経験自体がまだない場合や、過去に服薬させたことのない種類の薬剤が処方された場合は、「嫌がらずに飲んでくれるかな」という不安があると思います。
大事なことは、保護者と子どもの双方がリラックスして臨むことです。保護者が硬い表情でおそるおそる服薬させることで子どもも不安になり、より警戒してしまう原因となります。
「薬を飲む前に、楽しい話をしてお子さんの緊張がとけていることを確認し、薬を飲むことに対して前向きな言葉をかけてあげてください。そして、いつもの自然な笑顔で服薬させてください」と伝えます。
あらかじめ保護者自身が薬の味を知ることは有用であると考え、当薬局では味についての情報にも重きを置いて提供しています。例えば、“子どもに受け入れられやすい甘い味である”ということが分かっていると、保護者も比較的安心して服薬させることができると思います。
それでも子どもは味やにおい、食感に敏感なため、実際に薬を口にすると抵抗を示すことがあるでしょう。ひとつの方法にこだわらずさまざまな方法を試してもらいます。
水または白湯で服薬させるのが原則ですが、市販されているゼリー状の服薬補助用品などを用いたり、飲み物や食べ物に混ぜて服薬させたりする方法もあります。製剤の特性上、苦みが増してしまう薬剤などもあるので、必要な情報は必ず伝えます。また、ミルクやおかゆなど主食に混ぜると、薬の味で主食が嫌いになることがあるので避けてもらいます。薬剤師自身の経験も織り交ぜて紹介することで、具体的な提案ができると感じます。
散剤では、少量の水を加え練ってペースト状にしたものを、口腔内の頬の内側や上顎に塗りつける、少量の水で溶いたものを、スポイトや注射器型の道具を使って頬の内側寄りに少しずつ注入するなどの方法もあります。
かわいい容器や、好きなキャラクターのコップやスプーンで気を紛らわせることも一助となる場合があります。シールなどのちょっとしたご褒美があると継続につなげやすくなります。親子で試行錯誤し、保護者も含めて負担なく実践できる方法を見つけてもらいます。
飲めたときにはしっかりと頑張りを褒めてあげて、症状が改善した際には「お薬頑張って飲んだからだね」と伝え、服薬意義への理解を深めていきます。

年齢が上がって理解力が高まれば、特に先天性疾患やアレルギーなどのある場合には「なぜ服薬しなければならないのか」を伝えてもらうことも大切です。薬剤師が直接説明する場合もありますが、その機会は少なく、できることも限られています。子どもから大きな信頼を得ている保護者が時間をかけて伝えていくのが最善であり、子どもへの分かりやすい伝え方を保護者にアドバイスすることも薬剤師の務めのひとつです。


子どもが体調不良になると保護者は大きな不安を抱きます。中には自分を責めてしまう方もいるので、「お子さんが苦しそうにしているとお母さん(お父さん)もつらいですよね」と共感を示した上で、治療により改善したときのことをイメージできるような声かけをして励まします。さらに、「お母さん(お父さん)が体調をくずさないようにご自身も大事になさって、困ったことがあればいつでも相談してくださいね」と、ねぎらいの言葉や安心につながる言葉をかけることも忘れないようにします。
薬のことに限らず、ネットやSNSには情報がたくさんありますが、ありすぎるがゆえに自分で判断するのが難しいという声を多く耳にします。そのような観点からも、かかりつけのクリニックや薬局を持つことをお勧めしています。また、地域の子育て支援イベントの情報や、子育て支援センターで保健師さんからアドバイスが得られることなどもお伝えしています。

当社ウェブサイトでは、ご利用者の利便性向上と当社サービスの向上のためCookieを使用しています。また、当サイトの利用状況を把握するためにCookieを使用し、Google Analyticsと共有しています。Cookieによって個人情報を取得することはありません。Cookieの使用にご同意いただきますようお願いいたします。詳しくはこちら